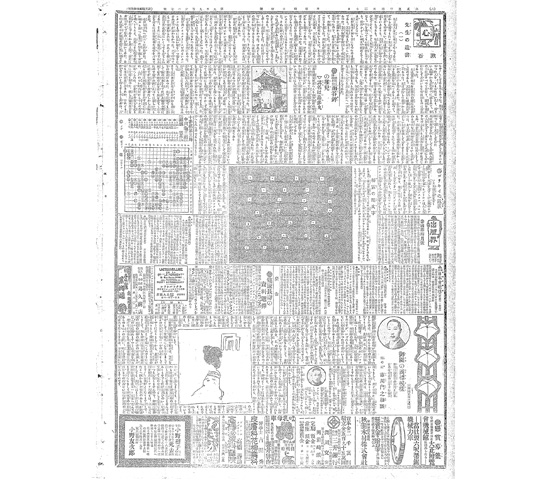ここから本文です
40歳で朝日新聞へ
東京帝大講師で教授が目前だった夏目漱石が、東京朝日新聞社に転職したのは40歳のときだった。「創作に専念したい」という強い思いからだ。
だが、権威ある地位、安定した職場を放り投げ、当時はベンチャー企業といってもいい新聞社に、中年すぎからの転職である。
覚悟がいる。条件を詰めねばならない。漱石は弟子を介し、こまかい取り決めを問い合わせた。
- 手当は月額いくらか。額は固定か累進か。
- 月俸200円、累進式なり。
- むやみに免職しないという保証はあるか。(主筆の)池辺(三山)氏あるいは社主によって保証されるか。
- ご希望とあれば正式に保証させる。
- 退隠料あるいは恩給とでもいうものの性質は。その額は在職中の手当の幾割に当たるか。それらの慣例はいかに。
- 草案はあるがまだ確定していない。早晩社則ができると信じる。まずお役所なみと見当をつけてほしい。
- 小説は年1回でいいか。その連続回数は。
- 年2回、1回100回くらいの大作を希望する。もっとも回数を短くして3回でもいい。
- 作品に営業部より苦情がでても構わぬか。
- そういうことは絶対的にないことを確保する。
- 雑誌に執筆する自由は。
- 従来からご関係の深い「ホトトギス」へはご自由に。ただ、小説はすべて本社が申し受けたく、また他の新聞には一切、執筆されないことを希望する。
実に詳細で具体的であり、近代的な契約の観念の表れだ。
小説記者の漱石は、毎日出社する義務はないが、週1回、編集幹部会には出席した。会議ではあまり発言しなかったが、時折思いがけぬ警句を吐いて笑わせた。漱石が会議に出ると何となく賑(にぎ)やかになった。終わって誘われると、近くの交詢社に食事に行った。
小説だけでなく随筆や評論も書いた。2年で終わってしまったが文芸欄も主宰し、編集者の仕事もこなした。関西であった大阪朝日新聞社主催の講演旅行も引き受け、4回も講演した。日本の近代化を論じた有名な「現代日本の開化」は、その時の講演だ。だが、真夏の講演旅行は病気持ちの漱石には過酷で、大阪で最後の講演を終えると倒れ、入院した。
強力な後ろだてになっていた池辺三山が、社の内紛から退社すると、漱石の立場は微妙になった。従来どおり、幹部から尊敬されてはいたが、機構改革もあり漱石は社内会議にでることもなく、家にこもって、創作に専念した。
在職9年、漱石作品の大部分は朝日新聞に掲載された。「明暗」執筆中に死去。直接の死因は持病の胃(い)潰瘍(かいよう)だったが、その濃密な仕事ぶりから、「過労死」という言葉が浮かぶ。

入社の辞漱石が朝日新聞入社時、紙面に発表
大学を辞して朝日新聞に這入(はい)ったら逢う人が皆驚いた顔をしている。
中には何故(なにゆえ)だと聞くものがある。大決断だと褒めるものがある。大学をやめて新聞屋になる事がさほどに不思議な現象とは思わなかった。余が新聞屋として成功するかせぬかは固(もと)より疑問である。成功せぬ事を予期して十余年の径路を一朝に転じたのを無謀だといって驚くなら尤(もっとも)である。かく申す本人すらその点については驚いている。しかしながら大学の様な栄誉ある位置を抛(なげう)って、新聞屋になったから驚くというならば、やめて貰(もら)いたい。大学は名誉ある学者の巣を喰(く)っている所かも知れない。尊敬に価する教授や博士が穴籠(あなごも)りをしている所かも知れない。二三十年辛抱すれば勅任官になれる所かも知れない。その他色々便宜のある所かも知れない。なるほどそう考えて見ると結構な所である。赤門を潜(くぐ)り込んで、講座へ這(は)い上(あが)ろうとする候補者は――勘定して見ないから、幾人あるか分らないが、一々聞いて歩いたらよほどひまを潰す位に多いだろう。大学の結構な事はそれでも分る。余も至極御同意である。しかし御同意というのは大学が結構な所であるという事に御同意を表(ひょう)したのみで、新聞屋が不結構な職業であるという事に賛成の意を表したんだと早合点をしてはいけない。
新聞屋が商売ならば、大学屋も商買である。
商売でなければ、教授や博士になりたがる必要はなかろう。月俸を上げてもらう必要はなかろう。勅任官になる必要はなかろう。新聞が商売である如(ごと)く大学も商売である。新聞が下卑た商売であれば大学も下卑た商売である。ただ個人として営業しているのと、御上(おかみ)で御営業になるのとの差だけである。
大学では四年間講義をした。
特別の恩命をもって洋行を仰つけられた二年の倍を義務年限とするとこの四月で丁度(ちょうど)年期はあける訳(わけ)になる。年期はあけても食えなければ、いつまでも嚙(かじ)りつき獅嚙(しが)みつき、死んでも離れないつもりでもあった。ところへ突然朝日新聞から入社せぬかという相談を受けた。担任の仕事はと聞くとただ文芸に関する作物(さくぶつ)を適宜の量に適宜の時に供給すればよいとの事である。文芸上の述作を生命とする余にとってこれほど難有(ありがた)い事はない、これほど心持ちのよい待遇はない、これほど名誉な職業はない。成功するか、しないかなどと考えていられるものじゃない。博士や教授や勅任官などの事を念頭にかけて、うんうん、きゅうきゅういっていられるものじゃない。
大学で講義をするときは、いつでも犬が吠えて不愉快であった。
余の講義のまずかったのも半分はこの犬のためである。学力が足らないからだなどとは決して思わない。学生には御気の毒であるが、全く犬のせいだから、不平はそっちへ持って行って頂きたい。
大学で一番心持ちの善(よ)かったのは図書館の閲覧室で新着の雑誌などを見る時であった。しかし多忙で思う様にこれを利用する事が出来なかったのは残念至極である。しかも余が閲覧室へ這入ると隣室にいる館員が、無暗(むやみ)に大きな声で話をする、笑う、ふざける。清興(せいきょう)を妨げる事は莫大(ばくだい)であった。ある時余は坪井学長に書面を奉って、恐れながら御成敗を願った。学長は取り合われなかった。余の講義のまずかったのは半分はこれがためである。学生には御気の毒だが、図書館と学長がわるいのだから、不平があるならそっちへ持って行って貰いたい。余の学力が足らんのだと思われては甚だ迷惑である。
新聞の方では社へ出る必要はないという。毎日書斎で用事をすればそれで済むのである。
余の居宅の近所にも犬は大分(だいぶ)いる、図書館員の様に騒ぐものも出て来るに相違ない。しかしそれは朝日新聞とは何等(なんら)の関係もない事だ。いくら不愉快でも、妨害になっても、新聞に対しては面白く仕事が出来る。雇人(やといにん)が雇主(やといぬし)に対して面白く仕事が出来れば、これが真正の結構というものである。
大学では講師として年俸八百円を頂戴していた。子供が多くて、家賃が高くて八百円では到底暮せない。仕方がないから他(ほか)に二三軒の学校を馳(かけ)あるいて、ようやくその日を送っていた。いかな漱石もこう奔命(ほんめい)につかれては神経衰弱になる。その上多少の述作はやらなければならない。酔興(すいきょう)に述作をするからだというならいわせて置くが、近来の漱石は何か書かないと生きている気がしないのである。それだけではない。教えるため、又は修養のため書物も読まなければ世間へ対して面目がない。漱石は以上の事情によって神経衰弱に陥ったのである。
新聞社の方では教師としてかせぐ事を禁じられた。
その代(かわ)り米塩(べいえん)の資に窮せぬ位の給料をくれる。食ってさえ行(ゆ)かれれば何を苦しんでザットのイットのを振り廻(まわ)す必要があろう。やめるなといってもやめてしまう。休(や)めた翌日から急に脊中(せなか)が軽くなって、肺臓に未曾有(みそう)の多量な空気が這入って来た。
学校をやめてから、京都へ遊びに行った。
その地で故旧(こきゅう)と会(かい)して、野に山に寺に社(やしろ)に、いずれも教場よりは愉快であった。鶯(うぐいす)は身を逆(さかし)まにして初音(はつね)を張る。余は心を空(そら)にして四年来の塵(ちり)を肺の奥から吐き出した。これも新聞屋になった御蔭(おかげ)である。
人生意気に感ずとか何(なん)とかいう。変り物の余を変り物に適する様な境遇に置いてくれた朝日新聞のために、変り物として出来得(できう)る限りを尽(つく)すは余の嬉(うれ)しき義務である。
(東京朝日新聞1907年5月3日、大阪朝日新聞の題は「嬉しき義務」同4・5日)
*このページで引用した夏目漱石の文章は岩波文庫と「漱石全集」(岩波書店)に基づいています。読みやすさを考慮し、一部の漢字をひらがなに置き換えるなど表記を変えました。